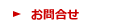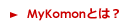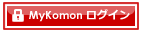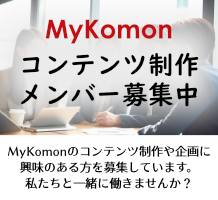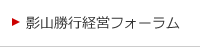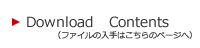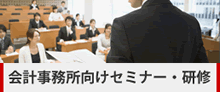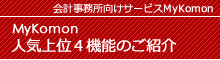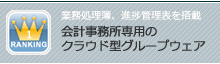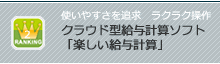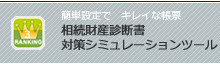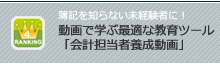3月13日、新しい文書回答事例が国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。
病理診断とは、患者の人体から採取した病変の組織や細胞を観察して病変を診断することを指し、平成20年の医療法施行令改正で、標榜診療科(病理診断科)として認められました。
厚生労働省から公表されている「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によれば、この「病理診断科」と標榜している一般診療所の施設数は、2023年(令和5年)10月1日現在、82施設となっています。
この「病理診断科」と標榜している一般診療所が、複数の保険医療機関と連携して病理診断を行うため、連携先ごとに本件病理診断に係る費用の支払等について契約を締結し、連携した保険医療機関が受領した診療報酬のうち当該契約で定められた額の支払を受けた場合の消費税の取扱いと、措置法26条の適用について、事前照会がなされています。
今回の事例の場合は、療養の給付として消費税は「非課税」、措置法26条の適用も可能、とし、東京国税局の審理課長も差支えない旨回答されています。
対象となる施設数が上記のとおり少数ではあるものの、契約の相手先である保険医療機関側の処理に留意しましょう。医療機関は血液検査などを検査会社へ外注していることがあります。このような場合は外注費として、消費税を課税処理にしているかと思います。
該当する取引があった場合に、同じような感覚で消費税を課税処理にしないようにしましょう。
さて、もう1つ問題なのが、個人事業税の取扱いです。
事業税は、社会保険診療報酬分は非課税となり、課税標準額の計算上、所得金額から差し引くことができます。
今回の事例の場合、同様に非課税となるのでしょうか。
事業税の取扱いは各自治体の判断が大きいため、これは直接申告先へ確認することとなるでしょう。
 連携病理診断の仕組みにより病理診断医が受領する診療報酬に係る税務上の取扱いについて 国税庁
連携病理診断の仕組みにより病理診断医が受領する診療報酬に係る税務上の取扱いについて 国税庁