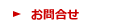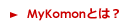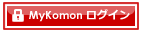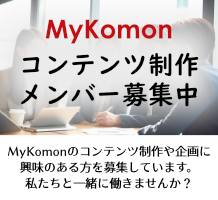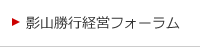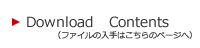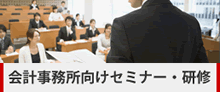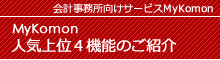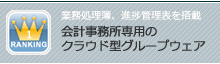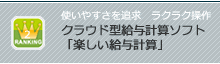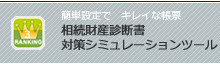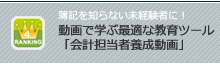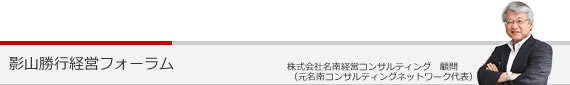
- 2026/02/10�@�ܗ^�̋��^���ɂ��Ă̌ږ�����������
- 2026/01/14�@1�l������ېʼn��i�͕ς��Ȃ��̂ɉېŊ����͑�����
- 2025/12/23�@�m��Ȃ������ɏ��n����Ă���……�ƂȂ�ʂ悤
- 2025/12/09�@�����y�n���ɋA�����x�ƁA�啪�̑�Ў���
- 2025/11/26�@�f�Ï��ׂ͖����Ă���̂Őf�Õ�V�̉���͕K�v�Ȃ��H
�@�����A����Ƃ𒆐S�Ɂu�ܗ^�̋��^���v�Ɏ��g�ގ��Ⴊ�A���f�B�A��ʂ��ĕ���Ă���B
�@������Ƃ̌o�c�҂�o���S���҂̒��ɂ��A�u�ܗ^���̋��^�Ɏ�荞�ނ��ƂŎЈ����Ƃɂǂ�ȃ����b�g�E�f�����b�g������̂��v�A�S�������Ă�����������̂ł͂Ȃ����H
�@�����ŁA����AI�Ɉē����̍쐬���˗����Ă݂��B�쐬���ꂽ���͈͂ȉ��̂Ƃ���B
|
�ږ��o�c�w�����F�ܗ^�̋��^���Ɋւ��邲�����i�ŗ��m�������쐬�j 1�D�͂��߂� �@���f����ς����b�ɂȂ��Ă���܂��B �@�{���́A�M�Ђ̐l����\���̌���������ђ������I�Ȍo�c��Ղ̋�����ړI�Ƃ��āA�u�ܗ^�̋��^���i�ܗ^�̈ꕔ�܂��͑S�������ዋ�^�֑g�ݑւ��鐧�x�j�v�ɂ��Ă������\���グ�܂��B �@�ߔN�A���Ƃ𒆐S�ɓ������i��ł���A�̗p�����͂̌���E�l����̕������E�i���x�v����ł́j�Љ�ی������S�̌������ɂȂ���\�������邱�ƂȂǁA�����̌o�c�����b�g���m�F����Ă��܂��B 2�D�ܗ^���^���̎�ȖړI �@�ܗ^���^���͒P�Ȃ鋋�^���x�ύX�ł͂Ȃ��A�l����̐헪�I�Đv�Ƃ��Ĉʒu�Â����܂��B �@���Ɉȉ���3�_���傫�ȖړI�ƂȂ�܂��B �@ �̗p�͂̋����i���C���E�����̌��h������j �@���l�s��ł́u�����v���ł��d�������w�W�ł��B �A �l����̕������ƃL���b�V���t���[�̈��� �@�ܗ^�x�����̑傫�ȃL���b�V���A�E�g������������A�N�Ԃ�ʂ��������J�肪�������܂��B �B �Љ�ی����̍œK���i���������ɂ��e���������₷���j �@���^�Əܗ^�ł͎Љ�ی����̏�����قȂ邽�߁A���������i�W����V���z�̓����j��ܗ^�����ɂ���ẮA�ܗ^���^���ɂ���ƁE�]�ƈ������ꂩ�A�܂��͑o���̕ی������S���ϓ�����P�[�X�������܂��B
3�D�N�����z�܂����M�Ђւ̉e���i���Z���ʂ̊T�v�j �@�M�Ђ̔N���т��ȉ��̂悤�ɉ��肵�A���̑O������̂��Ƃŏܗ^���^���̉e�������Z�������܂����B
�@���̕��z�ł́A���N���w��30�����݂��邽�߁A����������ܗ^�z�ɂ���ẮA�ܗ^�ƌ����ɂ�����Љ�ی����̏���̉e���������₷���\���Ƃ����܂��B �i���Z��j
4�D�]�ƈ����̃����b�g �@�ܗ^���^���͏]�ƈ��ɂƂ��Ă������̗��_������܂��B
�@���Ɏ�N�w�́u�����̎��肪���肷�邱�Ɓv�������]������X��������A�K�Ȑ��x�v�Ɛ������s�����Ƃ��蒅������ɂ���^���܂��B 5�D��Ƒ��̃����b�g�i�����j �@�ܗ^���^���̓����ɂ��A��Ƃ͈ȉ��̌��ʂ����҂ł��܂��B �@ �̗p�����͂̌��� �@�������オ�邱�Ƃŋ��l�[�̑i���͂����܂�A�D�G�Ȑl�ނ̊m�ۂ��e�ՂɂȂ�܂��B �A �l����̕����� �@�ܗ^���̎������S���y������A�N�Ԃ̃L���b�V���t���[�����肵�܂��B �B �Љ�ی����̍œK�� �@���ɍ��N���w�̑�����Ƃł́A��ƕ��S�̕ی������������A�����I�Ȑl����팸�ɂȂ���܂��B �C �o�c�Ǘ��̓��������� �@���ዋ�^�������邱�ƂŁA�l����̗\�Z�Ǘ�����萸�k�ɂȂ�܂��B 6�D�����ɂ������Ă̗��ӓ_ �@�ܗ^���^���ɂ̓����b�g����������A�ȉ��̓_�ɔz�����K�v�ł��B
�@���������Ƃ��āA���x�v����]�ƈ����������̍쐬�܂ň�т��ăT�|�[�g�\�ł��B 7�D�܂Ƃ� �@�ܗ^���^���́A�u�̗p�͂̋����v�u�l����̕������v�u�Љ�ی������S�̌������̉\���v�Ƃ���3�̊ϓ_����A�M�Ђ̒������I�Ȍo�c��Ղ��������邽�߂̗L�͂Ȍ����e�[�}�̈�ł��B �@���ɋM�Ђ̔N�����z�ɂ����ẮA����������x�v�̓��e�ɂ���ẮA��ƁE�]�ƈ������ꂩ�A�܂��͑o���̎Љ�ی������S�ɉe����������\��������A�ʂɎ��Z�E�������s���Ӌ`�͑傫���ƍl�����܂��B |
�@���̂܂g�p����ɂ́A�܂��\���Ƃ͌����Ȃ��B������v���镔�������邪�A���������_�_�����Ƃ��Ă͗L�p�ŁA������ݏo�����߂̏����l�Ƃ��āA����AI�͒����ɐi�����Ă��Ă���B
�@�����Ƃ��A�����ŗ��p����ۂɂ́A����AI�̉��e���\���Ɋm�F�E�������������Ŕ��f����K�v������B������含�����߂��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��A���̐ӔC�����p�Ҏ��g�ɂ���Ƃ����_���Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
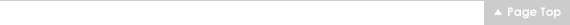
�@�ߘa7�N12���ɁA���Œ��y�ъe���ŋǂ���u�ߘa6�N���@�����ł̐\�����т̊T�v�v�����\���ꂽ�B
�@�����I�Ȃ��Ƃ́A
- �\�����̒�o�ɌW��푊���l�̐��́A166,730�l�i�O�N��107.1���j
- �ېʼn��i�̑��z�́A23��3,846���~�i��108.1���j
- �\���Ŋz�̑��z�́A3��2,446���~�i��108.0���j
�@���������b�T���z��������������������27�N���ȍ~�ōō��ɂȂ����B
�@�S���y�ѓ������ŋǂ̐\�����т���A��ȓ����_���r����ƁA
�i���j�J�b�R���͑ΑO�N��
| �S�� | ���� | |
|---|---|---|
| �ېŊ����i���j | 10.4�i+0.5�|�C���g�j | 16.2�i+0.8�|�C���g�j |
| �ېʼn��i�i���~�j | 233,846�i108.1���j | 86,522�i108.1���j |
| �Ŋz�i���~�j | 32,446�i108.0���j | 14,250�i105.8���j |
| �푊���l1�l������ېʼn��i�i���~�j | 14,025�i101.0���j | 16,209�i100.0���j |
| �푊���l1�l������Ŋz�i���~�j | 1,946�i100.8���j | 2,670�i97.9���j |
�m�o�T�n���Œ����\�����E�������ŋnj��\�������쐬
�@�S�����������A�ېʼn��i�̑ΑO�N�L�ї���1���߂��㏸�����Ă�����̂́A�푊���l1�l������ېʼn��i�́A�ΑO�N�ł͐L�тĂ͂��Ȃ��B�������ېŊ����͑S����10.4���A�����Ǔ���16.2���Ƌ}�����Ă���B
�@���_�ł͂��邪�A
- �s���Y���i�i���ɓs�s���}���V�����j���㏸
- ���Z���Y�������i�����㏸�j
- ����҂̎��Y�ۗL������
�Ȃǂɂ��A�u��b�T���M���M���̑w�v���ېő��ɗ��ꍞ��ł���B�܂�A
- 1���~�ȏ�̕x�T�w → ���Ƃ��Ɖې�
- 3,000��〜7,000���~�w → �����������ĉېőΏۂɓ���
�@���������X���͂��炭�������낤�B
�m�Q�l�n���Œ��u�ߘa6�N���@�����ł̐\�����т̊T�v�v
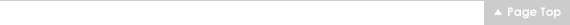
�@�����@�\�̉^�c�������Ə��p�E���p���x���Z���^�[���������A2025�N5��20���Ɍ��J���ꂽ�B����ɂ��Ɓu��O�ҏ��p�̐������ߋ��ō����X�V�v�Ƃ������B
- �ߘa6�N�x�̎��Ə��p�ɌW�鑊�k�Ґ���23,000�҂���
- �Z���^�[�J�݈ȗ��̗v����15���Ғ��ƂȂ���
- �ߘa6�N�x����O�ҏ��p�̑��k�Ґ���16,045���A�v��119,294�҂ɒB����
- �ߘa6�N�x����O�ҏ��p�̐�����2,132���ƁA�ߋ��ō����L�^����
- ��O�ҏ��p�̐����͗v��12,306���ŁA�Α��k�Ґ���Ŗ�10.3���ƂȂ���
�@������n��Ƃ̋Ǝ�́A�T�[�r�X�ƁA�����ƁA���E�����ƁA�h���E���H�T�[�r�X�ƁA���Ƃ���ŁA����K��1���~�ȉ�����68�����߂Ă���B
�@���{������Z������5���Ɍ��\�����u���Ə��p�}�b�`���O�x���v�����тɊւ��郌�|�[�g�ɂ��ƁA
- �ߘa6�N�x�̈������킹����709���i�O�N��106.5���j
- ����163���i�O�N��158.3���j
- �ߋ�6�N�Ԃ̈������킹���̗v��2,058��
- �����ԓ�������331���i��16���̐��j
- ���n���͔N����5�疜�~�ȉ���7���A���n���i��500���~�ȉ���5��
- �Ԏ���Ƃ̐������3������
- �ߘa6�N���I�[�v���l�[���Ō�p�҂̌���ɑ�48�Ђ̎��Ǝ҂��Q������
�@���̂悤�ɁA���Z���ɂ������K�͂̎��Ə��p�̎��g�݂����������Ă��Ă���B
�@�{�茧�ɋ��_��u�����C�g���C�g���^�c����u�I�[�v���l�[�����Ə��prelay�i�����C�j�v�́A���Ə��p�̃}�b�`���O���I�[�v���l�[���ōs���A��p�҂�����@�Ő���L���Ă���B����relay�����\�����j���[�X�����[�X�ɂ��A
- 2020�N�̃T�[�r�X�J�n�ȗ��A��800���̌�p�ҕ�W�Č��ɑ���160���̐�����������
- relay�ɂ͖�������ƃv���~�A�����������A��������ł��Ж�����̊�Ə��͉{���ł���
- ����110�̎����́E���H�c�́E�x���Z���^�[�Ƃ̘A�g���i��ł���
- �o�Y�Ȃ́u������Ǝx�����ƕ⏕���v�ɍ̑�����Ă���
- ���t�{�́u�W�l���n�o�E�g��̂��߂̑Η����i���Ɓv�ɂ��̑�����Ă���
�@����͓��ɁA�n�Ǝ҂̍����e�����p�̕s�����ŁA�܂��܂��u��O�ҏ��p�v�ɂ�鎖�Ə��p����������������B���K�͊�Ƃ̐ŗ��m�́u�m��ʂ����ɏ��n����Ă����v�ƂȂ�Ȃ��悤�A�֗^���Ƃ̏��p���ɒ�������p�����d�v�ɂȂ邾�낤�B
�@�@���Ȃ����v�ɂ��ƁA�ߘa7�N10�������_�������y�n���ɋA�����x�̐\��������4,556���B���̂����A�����F�߂�ꂽ�̂�2,145���ŁA�A���̏��F�����͖�47���ƂȂ�B
�@�����x�̊T�v���܂Ƃ߂��
- �ߘa5�N4���J�n�B�����l�ɂƂ��ĕs�v�ȓy�n�A�ێ��Ǘ�������ȓy�n���Ώ�
- �K�v�ƂȂ��p�́A�����u1�M������14,000�~�̐R���萔���v�Ɓu1�M������20���~�̕��S���v
- �\�������̂����A�p����74���A�s���F��74���ŁA�S�̂̐����ɉ߂��Ȃ�
- ����������y�n�A�S�ی����ݒ肳��Ă���y�n�A���l�̗��p���\�肳��Ă���y�n�A�����y�n�A���E�����炩�łȂ��y�n���́A�p���̑Ώ��ɂȂ�
�@���ɁA�A�����F��̓o�L���̈����ɂ��Ă�
- �ʏ�Ɠ��l�̏��L���ړ]�o�L���s���
- ���L�җ��ɂ́u���i������b�j�v�ƋL�������
- �n�ځE�n�ς͏]���̓o�L���e�������p�����
- �o�L�����u���ɋA���y�n�v�Ƃ��������ʂȕ����⒍�L�͂Ȃ�
- �����I�ɏ����i���p�E�ݕt�j���s����ꍇ�ɂ́A���L���Y�̍L������D���Ƃ��Č��J�����
�@��n�ɒ��ڂ���ƁA�\��������1,588���A����ɑ��A�������F���ꂽ������784���ŁA���ɏ��B
�@��̑啪���̉Ў��̂ł́A�đ�������170���̂����A�Ƃ���70���ƌ����邱�Ƃ����o�����B�Ƃ����ׂđ����y�n�Ƃ͌���Ȃ����A���������āi�\�Ȃ玩���̂̕⏕�����j�ōX�n�ɂ��A���ɋA�����x���g���Ă�����A���̑�Ў��̂̉e���͌y���ł�����������Ȃ��B�����̂̕����R�X�g���A�啝�ɍ팸�ł����ł��낤�B
�@���N�x�̐f�Õ�V����̋c�_���u�������x���R�c��v�Ŏn�܂��Ă���B
�@11��11���Ɍ��J���ꂽ�������x���ȉ�̔z�z�����ŁA��Ö@�l�̕a�@�E�����f�Ï��̎��v�E��p�\�����ڍׂɏq�ׂ��Ă���B
�@�ߘa5�N�ɒ�߂�ꂽ�u�S�Ă̈�Ö@�l�̌o�c�������Z��3�����ȓ��ɒ�o�v�`�����ɂ��A�n��̑�a�@��Ö@�l���l��t��Ö@�l�̎��v�E��p�\�������炩�ɂȂ����B
�@���o�V����11��5���t�̋L���̌��o���ɁA�u�o�험�v���A�f�Ï�6.4���E�a�@0.1���v�Ƃ������B�a�@�o�c�����炩�ɋꂵ���A�f�Ï��̌o�c�ׂ͖����Ă���A�Ƃ̈�ۂ�^����悤�ȏ����o���ŁA����̐f�Õ�V�̉���́u�a�@�̑��z������s���ׂ��v�Ƃ̕�������ł��o���Ă���悤���B
�@���R�c��z�z�������ڍׂɌ����
| �a�@ | �f�Ï��i��Ö@�l�j | |
|---|---|---|
| ���ς̔N�Ԏ��v���z | ��36���~ | ��1.9���~ |
| ���ς̔N�Ԍo��z | ��36���~ | ��1.7���~ |
| ���^��z | ��19���~�i52.6���j | ��9,400���~�i48.3���j |
| ���@�@�����^�� | ��2,600���~ | ��2,700���~ |
| ���^��ȊO�̌o�� | ��17���~ | ��8,200���~ |
�m�o�T�n������HP�u�������x���ȉ�i�ߘa7�N11��11���J�Áj�����v���쐬
�@�����f�Ï��ł͕��ώ��v��13.7�����@����V����߁A�����v����2,000���~���������ԂƂȂ��Ă���B���̂��ߍ���̉���Ɋւ��ẮA���ɐf�Ï��ւ̑��z�͊��҂ł��Ȃ����ƂɂȂ邩������Ȃ��B
�@���̔z�z�����ɂ́u��t���^�̍��۔�r�v�̃f�[�^���Y�t����Ă���A�ȉ��̂悤�ɕ���Ă���B
- ��t�̋��^�����͍����i�S�Y�Ɓj���ς�4.5�{�A�Ζ����2.5�{
- OECD�����̈�t���^�͍����i�S�Y�Ɓj���ς�2.9�{�A�Ζ����2.1�{
- ���{�̈�t���^�����͍��ۓI�ɂ݂Ă������A�����f�Ï��̉@���̋��^�����ɂ��ẮAOECD�̊J�ƈ�Ƃ̔�r�ɂ����Ă��傫���������Ă���
�@�a�@�͌��݂̕�������l������̉e�����Čo�c�Ƀ_���[�W���Ă���B�������f�Ï��͉@���̍������^�����ł����v���l�����A�o�c���Ԃ͗ǍD�B�u�f�Õ�V�v�̑��z����͕K�v�Ȃ��B
�@�z�z�����͂����i���Ă���悤���B
�m�Q�l�n
�����ȁu�������x���ȉ�i�ߘa7�N11��11���J�Áj�����ꗗ�v