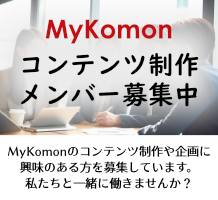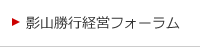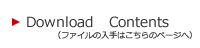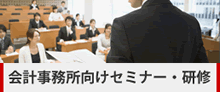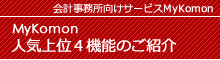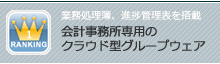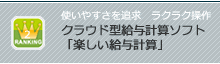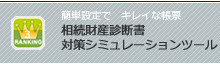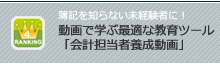1人当たり課税価格は変わらないのに課税割合は増える
令和7年12月に、国税庁及び各国税局から「令和6年分 相続税の申告事績の概要」が公表された。
特徴的なことは、
- 申告書の提出に係る被相続人の数は、166,730人(前年比107.1%)
- 課税価格の総額は、23兆3,846億円(同108.1%)
- 申告税額の総額は、3兆2,446億円(同108.0%)
いずれも基礎控除額引き下げがあった平成27年分以降で最高になった。
全国及び東京国税局の申告事績から、主な特徴点を比較すると、
(※)カッコ内は対前年比
| |
全国 |
東京 |
| 課税割合(%) |
10.4(+0.5ポイント) |
16.2(+0.8ポイント) |
| 課税価格(億円) |
233,846(108.1%) |
86,522(108.1%) |
| 税額(億円) |
32,446(108.0%) |
14,250(105.8%) |
| 被相続人1人当たり課税価格(万円) |
14,025(101.0%) |
16,209(100.0%) |
| 被相続人1人当たり税額(万円) |
1,946(100.8%) |
2,670(97.9%) |
[出典]国税庁公表資料・東京国税局公表資料より作成
全国も東京も、課税価格の対前年伸び率は1割近い上昇をしているものの、被相続人1人当たり課税価格は、対前年では伸びてはいない。しかし課税割合は全国で10.4%、東京管内で16.2%と急増している。
推論ではあるが、
- 不動産価格(特に都市部マンション)が上昇
- 金融資産が微増(株価上昇)
- 高齢者の資産保有が増加
などにより、「基礎控除ギリギリの層」が課税側に流れ込んでいる。つまり、
- 1億円以上の富裕層 → もともと課税
- 3,000万〜7,000万円層 → ここが増えて課税対象に入る
こうした傾向はしばらく続くだろう。
[参考]国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」


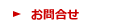
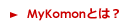
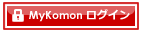









 1人当たり課税価格は変わらないのに課税割合は増える
1人当たり課税価格は変わらないのに課税割合は増える