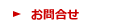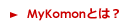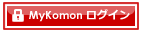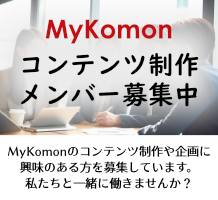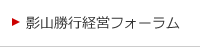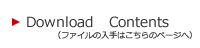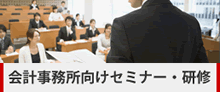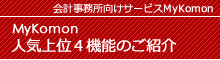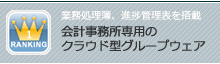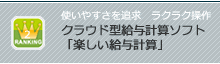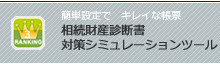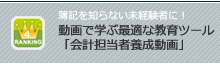作成日:2025/11/19
税務行政におけるオンラインツールの利用 Q&Aが公開 国税庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけとして、Web会議システム等のオンラインツールの利用が拡大しました。今や業務に手放せない方も多いのではないでしょうか。
これは税務行政についても同様で、感染防止のため対面機会を減らすことを目的に、まずは大企業を中心としたオンラインツールの利用が始まりました。その後、令和5年7月から対象を大規模法人へと拡大、そして令和7年10月からは、まずは金沢国税局・福岡国税局およびこれらの管内税務署において、納税者の規模関係なくオンラインツールの利用が始まりました。
○税務行政におけるオンラインツールの利用について
ここでのオンラインツールとは、次の4つが挙げられています。
- 連絡やデータ受渡しの手段として、メールの利用
- データ受渡しの手段として、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)の利用
- 打ち合わせ等の手段として、Web会議システム(Microsoft Teams)を利用
- アンケート回答用に、アンケート作成ツール(Microsoft Forms)を利用
オンラインツールの利用は、双方合意のもとでの利用を前提としているため、納税者側がオンラインでと希望したところで必ずしも受けてもらえるとは限らないという点に注意しましょう。逆も然りです。
上記他、オンラインツールの利用に関する、Q&Aが公表されています。
○税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(令和7年11月)(PDF/268KB)
現在のところ、次の18問が用意されています。
【利用に関する一般的な事項】
問1 どのような場面でオンラインツールを利用することができるのでしょうか。
問2 税務調査においてオンラインツールを利用する場合、調査の一連の手続きは全てオンラインで完結するのでしょうか。
問3 登録したメールアドレスを変更したいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。
問4 現在、税務署の税務調査においてオンラインツールを利用しているのですが、転居等により納税地が変わった場合、オンラインツールの利用を継続するには手続きが必要でしょうか。
問5 私は税理士です。以前、税務署の税務調査においてオンラインツールを利用したことがあります。今回、同じ税務署において別の税務調査が行われますが、オンラインツールを継続して利用することはできますか。
問6 税務調査等において、関与税理士がいる場合、納税者と税理士の双方がオンラインツールを利用するには、それぞれが利用のための手続きをする必要があるのでしょうか。
問7 オンラインツールを利用するため、アプリのダウンロードなどの準備が必要なのでしょうか。
問8 登録するメールアドレスに制限はありますか。
問9 オンラインツールの利用は、全ての国税局・税務署で利用することができるのでしょうか。
【セキュリティに関する事項】
問10 オンラインツールでは、個人情報などの機密性の高い情報を取り扱うのでしょうか。
問11 他人がメールアドレス等を登録することによるなりすまし行為が生じるおそれはないのでしょうか。
問12 税務署等において、インターネットメールの誤送信防止のためにどのような対策をとっているのでしょうか。
【各ツールの利用に関する事項】
問13 申告書や各種届出書等をインターネットメール又はPrimeDrive により提出してもよいのでしょうか。
問14 インターネットメールやPrimeDrive により資料のデータを提出する場合、データ容量やデータ形式の制限はありますか。
問15 税務調査等において、税務署等から、インターネットメールやPrimeDrive により資料を提供してもらうことは可能でしょうか。
問16 Microsoft Teams には録音・録画や文字起こしなどの機能がありますが、税務調査や行政指導においてこれらの機能を使用してもよいのでしょうか。
問17 税務調査等において、インターネットメールではどのような連絡が行われるのでしょうか。
問18 利用者が税務署等に電子データを提出する場合、どのような手段があるのでしょうか。
問16では、機能制限について確認しています。具体的には、Microsoft Teams にある、録音・録画、チャット、文字起こし(トランスクリプション)及びホワイトボード機能の利用は禁止している、という点です。ただし、画面共有について納税者や税理士側から使用することに問題はないようです。(税務署側からは行わないらしい)。
メールもオンラインストレージサービスもデータの受渡しが可能ですが、データ形式や容量、履歴確認の有無等によって使い分けるとよいでしょう。
今後順次利用する局(税務署)を拡大する予定のようです。今は関係なくても、そのうち関係してくると捉えれば、どういった取組が行われているか程度は確認しておかれるとよいのではないでしょうか。
なお、対税理士については、別途ページが設けられています。上記URLへのリンクもありますが、こちらからご確認いただくとよいでしょう。
○税理士事務におけるオンラインツールの利用について
関連コンテンツ:

税務行政におけるオンラインツールの利用 Q&Aが公開 国税庁
 税務行政におけるオンラインツールの利用 Q&Aが公開 国税庁
税務行政におけるオンラインツールの利用 Q&Aが公開 国税庁