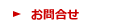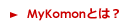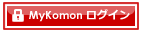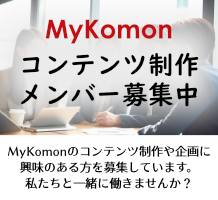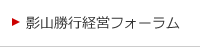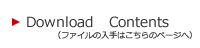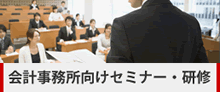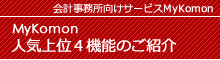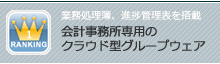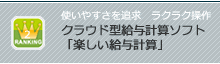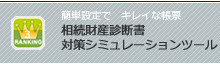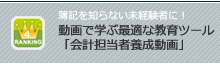作成日:2025/01/27
住宅ローン控除の調書方式 マイナポータル連携のFAQが公表 国税庁
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の年末借入金残高証明書について改正がされ、原則提出不要となりました。
仕組みとしては、従前は
金融機関→納税者→税務署(2年目以降年調時は勤務先) の流れで、年末借入金残高証明書の書類(データ)が流れていきます(いわゆる「証明書方式」)。
これが、改正後は、
金融機関→税務署→納税者 の流れで、年末借入金残高のデータが流れていきます(いわゆる「調書方式」)。
税務署→納税者 の流れとするには、マイナポータル連携が必須です。
このマイナポータル連携についてのFAQが、1月6日付で、国税庁サイトに公表されました。
○住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)
実務上、この改正が適用されるのは令和6年居住分からで、今回の確定申告から開始されることになります。
該当される方は一読されるとよいでしょう。
なお、2年目以降も税務署から通知をしてもらうには、1年目の申告時にe-Taxによる控除証明書の交付を希望する必要があります。
これをしない場合には、金融機関から受け取る返済予定表などを基に自ら残高を算定しなければなりません。
この調書方式については経過措置があり、システムが間に合わないなど金融機関側でこの方式が採用できない場合には、従前の証明書方式が継続できます。
ちなみに、この調書方式に移行した金融機関は、令和6年12月時点として国税庁が公表している数で40行、そのうち令和6年分から対応している数は20行にも満たない数です。そのため適用は令和6年居住分からとはいえ、大多数が従来の方式を採用しているものと思われます。
○年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧
どの程度今回の確定申告で利用されるかは不明ですが、事業者にとっては、令和7年分の年末調整から目にする可能性が生じます。年末借入金残高証明書の提出を受ける・受けないの判断に気をつけましょう。
関連コンテンツ:
 住宅ローン控除の調書方式 マイナポータル連携のFAQが公表 国税庁
住宅ローン控除の調書方式 マイナポータル連携のFAQが公表 国税庁